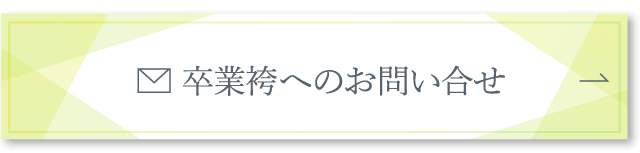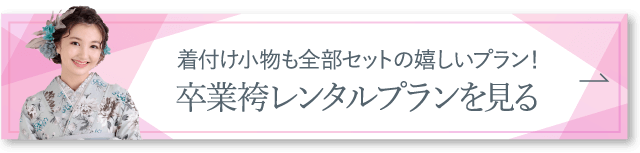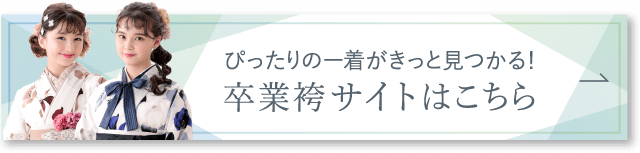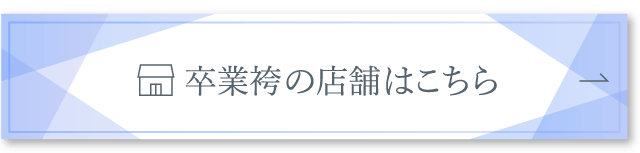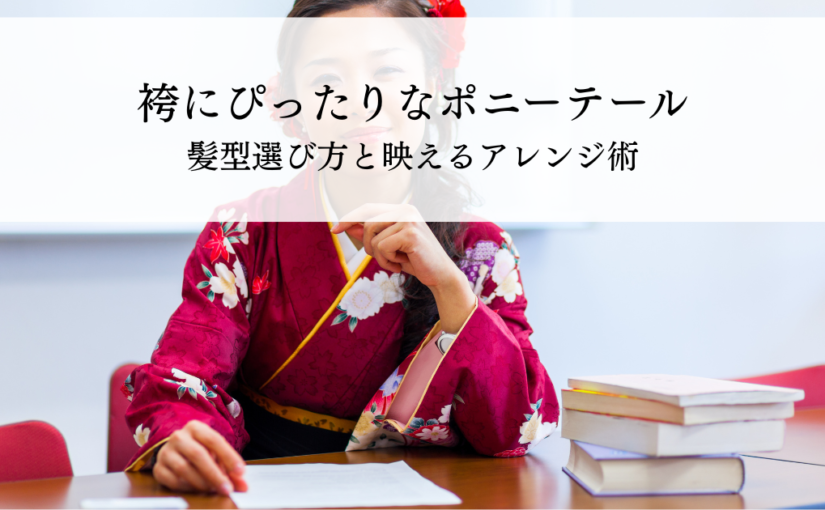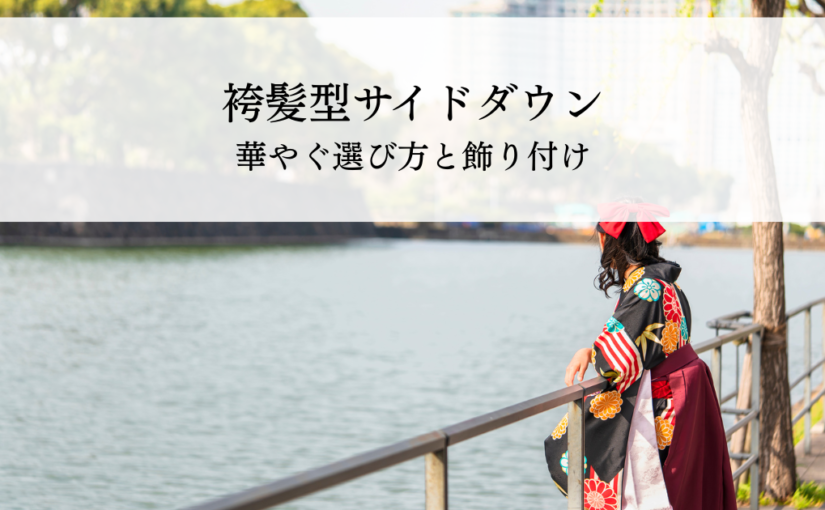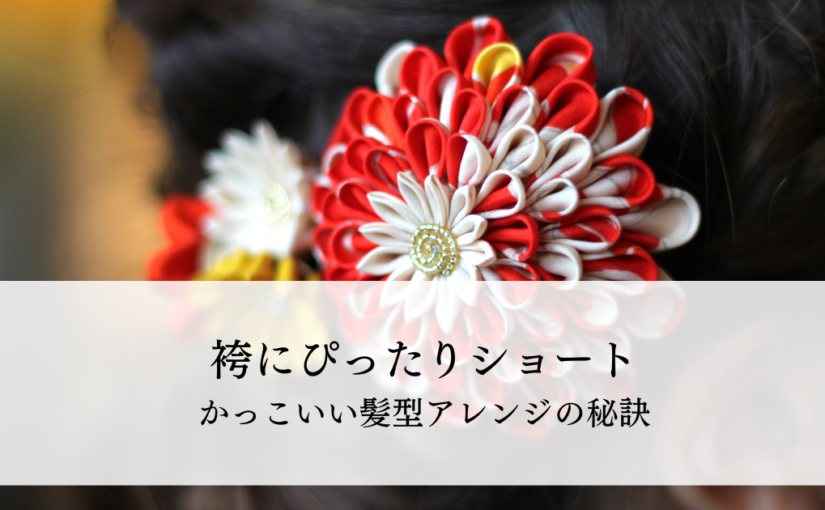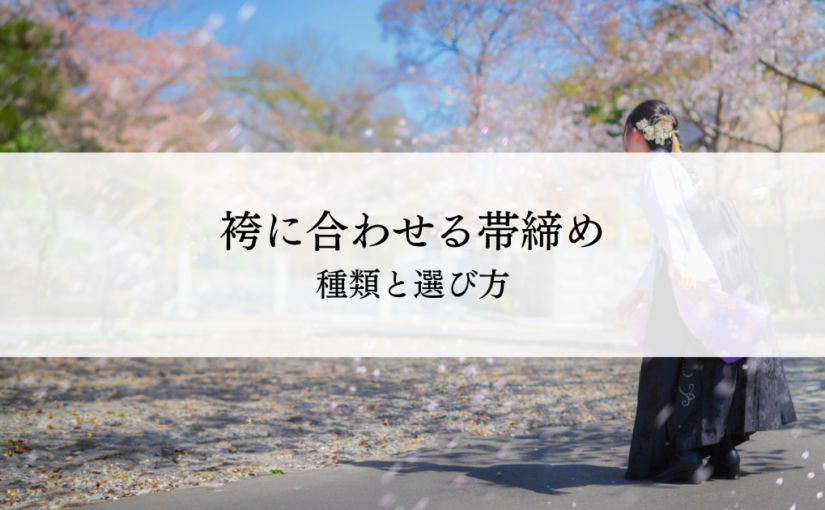袴は日本の伝統的な衣服であり、その多様な種類や着こなしは多くの人々を魅了しています。
特に、厳かな場面や特別な装いで用いられることの多い袴には、様々な歴史的背景やデザインが存在します。
今回は、数ある袴の中でも、その奥ゆかしさと格式高さで知られる「上黒袴」に焦点を当て、その魅力に迫ります。
伝統を守りつつも洗練された装いを求める方へ、その理解を深める一助となれば幸いです。
袴とは
袴の定義
袴とは、日本の伝統的な衣服の一種で、腰から下に着用するボトムスを指します。
丈が長く、裾が分かれていない「行灯袴(あんどんはま)」と、裾が二つに分かれた「馬乗り袴(うまのりばかま)」の二種類が主な形として知られています。
武士や学者などが着用した歴史があり、現代では主に卒業式や結婚式、茶道、武道などの場面で用いられています。
袴の種類
袴には、着用する場面や身分によって様々な種類が存在します。
男性用のものとしては、元々、儀礼や武士の装束として用いられていたものが多く、色や素材、文様によって格式が異なります。
女性用の袴は、明治時代以降に女学生の制服として広まったものが起源とされ、振袖や二尺袖といった着物と合わせて着用されるのが一般的です。
現代では、素材やデザインも多様化し、幅広いシーンで親しまれています。

上黒袴の魅力
上黒袴の特徴
上黒袴(うわぐろはかま)は、その名の通り、黒色を基調とした袴のことを指します。
特に、儀礼や正装として用いられることが多く、深い黒色が持つ落ち着きと威厳が特徴です。
素材には、正絹(シルク)などが使われることが多く、光沢やドレープ感が上品な印象を与えます。
腰板(こしいた)の部分に家紋が入ることもあり、より格式高い装いを演出します。
そのシンプルな色合いゆえに、合わせる着物や帯によって様々な表情を見せることができるのも魅力です。
上黒袴の着こなし
上黒袴は、その格式の高さから、主に成人式、結婚式(新郎や親族)、茶道、武道、神職の装束など、改まった場での着用が適しています。
男性が着用する場合は、紋付羽織袴(もんつきはおりはかま)の一部として、黒羽二重(はぶたえ)の着物と合わせることが最も正式な装いとされます。
女性が成人式などで着用する場合は、振袖や小振袖(二尺袖)といった華やかな着物と合わせることが多く、黒色の袴が着物の色柄を引き立て、大人っぽい雰囲気を醸し出します。
帯は、着物や場面に合わせて、金銀の帯や落ち着いた色の帯などが選ばれます。

まとめ
袴は日本の伝統的な衣服であり、その種類は多岐にわたります。
中でも上黒袴は、深い黒色が持つ落ち着きと格式高さが特徴で、改まった場にふさわしい装いを演出します。
男性の第一礼装から、女性の成人式や特別な装いまで、様々なシーンでその魅力を発揮します。
合わせる着物や帯によって印象が変わるため、TPOに応じた着こなしを楽しむことができます。
上黒袴を理解し、その奥ゆかしさを知ることで、日本の伝統文化への理解も一層深まるでしょう。
https://kinenbi.mai-jp.net/detail/?id=166119
こちらのページでは、シックな黒地に愛らしい小花柄が映える着物と、淡いピンクの袴を合わせた可憐な卒業袴を紹介しています。
黒とピンクのコントラストが絶妙で、大人っぽさの中に少女のような可愛らしさを感じさせる、レトロモダンな雰囲気が魅力です。
帯周りにのぞく市松模様がアクセントになり、晴れの日の装いをより一層おしゃれに演出しています。
ぜひリンク先で詳細をご覧いただき、その素敵なコーディネートをご確認ください。